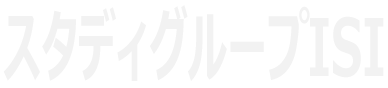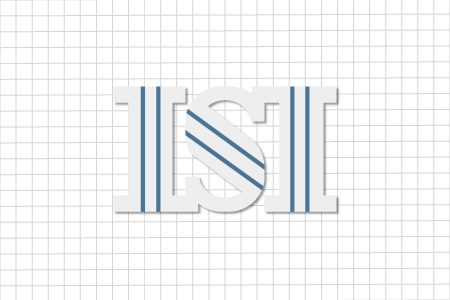「歯原性角化嚢胞の症例で歯槽骨保存のために考えた治療法」
今井歯科クリニック(水戸)今井文彰
ある日、高校時代の友人からその奥さんの口腔内を見てほしいとの電話があった。
この患者さんと39年間の付き合いの始まりであった。
上顎の半面が腫脹したこの患者さんは、当院で3件目とのことであった。上顎が腫脹したため、主婦であるこの患者さんは、まずは近所の歯科医院を訪れたが、その先生はX線写真も撮らず、腫れ止めの薬を処方されただけであった。
薬が無くなるとまた腫れるので、2件目の歯科医院を訪れたが、そこでは「口腔外科で手術だ。」と言われた。驚いた友人と奥さんが、そのことを確かめに来院したのである。
私も当院での初診を行い、当時の国立水戸病院の口腔外科を紹介した。
国立水戸病院では、病理検査を行い、この病名は「歯原性角化嚢胞」であることがわかった。
歯原性角化嚢胞は、良性の嚢胞であるが、娘(ドーター)嚢胞が除去後も出来やすいとのことで、嚢胞の除去と周囲の歯槽骨の除去も必要と聞いた。
私は、口腔外科の先生に、手術はなるべく歯牙と歯槽骨を保存することを条件に、手術をお願いした。
これが、39年間に4回行われる手術となる。
本日は、39年間の治療の軌跡を振り返りながら、私の患者さんとの付き合い方、治療の工夫などを会員の皆様とディスカッションしていきたい。